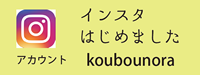季節の便り
あけましておめでとうございます。
しばらくインドに行ってたので長野は寒ーい、真白く美しい凍りの世界だ。
インドは、初めてホームステイをした。いつもの仕事のパートナーの家だ。
その歓迎ぶりには感謝なのだー。次々でてくる、お菓子、料理。おいしいので、パクパク食べてしまって、ついにもう食べれなくなるまでお腹がいっぱいになってしまった。というのは、仕事の打ち合わせを数日間、朝から夜まで家でやっていたからだ。泊まっている家はサッシ、ガラスではないので、外の音がよく聞こえる。
夕方 子供たちの遊ぶ声、
深夜 犬の泣き叫ぶ声、
早朝 くるまの音、鳥の声、
朝 人の声、くるまなどなど
たしか、私の子供の時代も夜は犬をはなしたりして、犬が歩いていた。なつかしい情景だ。
ワークシェアーというのだろうか、家庭に洗濯機がないので、洗濯ものを洗いにくる人がくる。そして、若い女の子は家事の手伝いをしにくる。ものにたよらず、人がやる。なにか基本的なことをインドにくると思い出す。それにしてもインドは、人の声も大きいし、よくしゃべるし、とてもにぎやか!
ほとんどの人が信仰を持っているインド人、もたない日本人。「神」というのは地球、自然の流れのような気がする。人が大事なものを忘れかけていく今の世の中とインドとの違いが、行く度に感じる。
帰国して、さっそく餅つき。
長野は今日も雪、真っ白い世界。朝焼けが美しい。
(2012年12月更新)

紅葉がきれい!
久しぶりに知り合いに会いたいのと木曽御岳を見たくて出かけた。御岳は20歳ぐらいの時、何回もきた。木曽の峠を朝から夕方までもくもくと歩いた。ほとんど御岳が見える峠だ。久しぶりにきた御岳は雄大な姿でかわっていなかった。でも、私がかわったせいか、昔のように心にしみいるようなものが感じられなく淋しかったが、人は昔の自分にはなかなかもどれない、本当に「今」しかないのだと痛感した。帰りに、18年くらい前、高山に月一回お話を聞きにいったチベット密教を教えてくださった人の処に寄らせていただいた。チベット密教といっても、当たり前の仏さまの教えを伝えていただいて、ふだんの暮らしの中ですっきりとした空気を吹き込んでくれた。自分しか見えていないことに気づかされた。朝日村にほとんど御自分一人で自宅兼寺を建てている。家の中に仏塔があり、奥さんとコツコツまだ作り続けている。すごい!
帰りに野麦峠を車で走った。ここも昔、一日歩いて日が暮れて、周りに民家もなくあわてていたところ、軽トラがきてのせてもらい、日和田村のその人の知り合いの農家に泊めてもらった。なつかしいところだ。カラ松がとても美しかった。
(2012年11月更新)
今年の夏は暑かった!仕事で東京に行く度にこの暑さにまいってしまった。長野、山梨は夜が涼しく、眠れることのありがたさを感じた。
日帰りで総勢5人スタッフと初めて佐渡へ行った。以前から夏の佐渡は好きで、一人でも出かけたが、久しぶりの佐渡だ。
なんという暑さ!おひさまはギラギラ!海が近いので暑さは尋常ではない。でも、この暑さは気持ちよい。汗をたくさん流して、きれいな海で泳いだ。一年に一回ぐらい、この暑さと太陽をあびるのも必要に感じた。なぜか、人間を取り戻したような気がした。
直江津発7時のフェリーで出かけて、9時半に着いて、ビール飲んで食べて、コンサート聞いて(アースセレブレーション)泳いで、温泉に入って、5時半発のフェリーで戻った。盛りだくさんのスケジュールだったが、来年はゆっくり行きた〜い!と思った。どうか、行けますように、、。
(2012年9月更新)
梅雨に入って草も勢いよく大きくなる季節になり、山のたけのこもスクスクのびて2〜3本ボキッと折って、夕食のおかずにしています。5月上旬発売の家庭画報に「工房野良」の服を掲載していただいた。遠州木綿を使った夏の衣を5点販売している。
木綿はなかなか気に入るものがなかったが、この浜松の綿に出会い、お洗濯も楽にできる布は夏にピッタリです。さすがにプロが着ると野良の服もよく見えるねエー
まけじと野良のスタッフ2人、自分でデザインしてそして縫って写真取り!
どうだい!負けないネエー
ちなみにこの服を購入希望の方は
①カタログを送ってもらう。
tel 0120-919-756
②インターネット
「家庭画報ショッピングサロン」検索
よろしくお願いします。
(2012年6月更新)